パーキンソン病を中心とした運動障害疾患の研究を行う順天堂大学大学院医学研究科神経学の研究グループは、Microsoftの MR(Mixed Reality)ヘッドマウントディスプレイ「HoloLens 2」と、空間を立体的にスキャンできる「Azure Kinect DK」を活用した双方向性 3 次元オンライン診療システム「Holomedicine」を開発。パーキンソン病専門施設PDハウス(以下PDハウス)を全国に展開・運営するサンウェルズ社と共同で実証実験を行うなど、実用に向けた取り組みを推進しています。


パーキンソン病患者へのオンライン診療の有効性を信じて研究を進める
1,000 人にひとり程度が罹患すると言われているパーキンソン病。手足のふるえや関節のかたさなどの運動症状が徐々に進行し、認知機能低下や便秘、不眠などの非運動症状を伴うこともある病気で、我が国においては高齢化の進展とともに患者数が増加しています。
パーキンソン病は根治療法がいまだ発見されておらず、薬物療法や手術療法などの対症療法が中心となっています。薬物効果は、内服のタイミングや患者の生活習慣などに大きく左右されると言われており、患者の状態に合わせて薬を調整することが、極めて重要になります。
したがってパーキンソン病は、専門医による適切な診療を定期的に受け続けられれば、症状を安定化させられる病気であるとも言えます。しかし、通院できる範囲に専門医がおらず適切な診療が受けられない場合は、症状が進みやすく、より一層通院が困難になる悪循環に陥ってしまいます。
こうした背景から、世界屈指のパーキンソン病の臨床・研究拠点として知られる順天堂大学大学院医学研究科脳神経学では、通院困難な患者も対面診療と同様の診療が受けられるオンライン診療の実現に向け、2014 年のビデオ通話による診療の有効性と安全性とを検証するパイロット研究を皮切りに、さまざまな取り組みを進めています。
「オンライン診療の研究自体はそれ以前にも行われていましたが、パーキンソン病のような慢性疾患に対して必要かどうかは議論が分かれるところでした」と振り返るのは、順天堂大学大学院医学研究科脳神学 准教授の大山 彦光氏。パーキンソン病は直接観察しなければ診断できない症状も多いため、2次元の画面越しで行われるオンライン診療は現実的ではないというのが大方の考え方だったそうです。
「ただ私たちは、症状が進行して通院できなくなり、適切な医療が受けられない患者さんがいることこそが大きな問題だと感じていました。オンライン診療はその問題を解決するための有効なアプローチであり、切り捨てるのではなく、どうすれば実現できるかという視点でコツコツと研究を進めてきました」(大山氏)。

離れた場所にいるお互いの姿を立体的に表示し、現実の診察室を再現する Holomedicine
パーキンソン病のオンライン診療を実現するためには、まず「2 次元の画面越しでは得られる情報が限られてしまう」という課題を解決する必要がありました。大山氏によると、当初理想としていたのは「SF映画でよく見る、ホログラムによる会議シーン」だったそうです。
離れた場所にいる人たちがまるで同じ空間で会話するような感覚をどうすれば実現できるのか。模索するなかで出会ったのが、2016 年に Microsoft が開発したリアルタイム 3 次元テレポーテーションシステム「Holoportation」について書かれた論文でした。その論文のなかで「Holoportation」は、遠隔地にいる人物の3D キャプチャを、HoloLens を通して複合現実として再現する仕組みとして紹介されていました。
大山氏は「これこそが私たちの考えていることを実現するソリューションになる」と直感し、日本マイクロソフトにコンタクト。ここから双方向性 3 次元オンライン診療システム「Holomedicine」の開発プロジェクトが大きく進展することになります。
Holomedicine は、HoloLens 2 と、Azure Kinect DK、PC、そして無線 LAN のネットワークで構成されています。Azure Kinect DK の 3 次元スキャナー機能を利用することで患者と医師それぞれの動作情報を捉え、無線 LAN を通じて双方のHoloLens 2 に転送、HoloLens 2 のディスプレイに相手の姿が 3 次元的に表示される仕組みです。
「私たちの技術力だけでは、理想とするシステムを構築するのは困難でした。そこで日本マイクロソフトさんに相談したところ、すぐに Holomedicine のプロトタイプとも言えるプログラムをつくって見せてくれました。そのプログラムには、まさに私たちがやりたいと思っていたことが表現されていて、感動したことを覚えています」(大山氏)。
順天堂大学医学部脳神経学講座 非常勤助教の関本 智子氏によると、Holomedicine の特徴は「医師だけでなく患者さんも HoloLens 2 を装着することでお互いの姿を立体的に見ることができるため、現実の診察室と近い雰囲気を再現できること」。
体を思い通りに動かせない症状がある患者にも HoloLens 2 を装着してもらうのは患者の負担を増やすように思えますが、実は双方が HoloLens 2 を装着し、互いの存在を近くに感じられるこの仕組みこそが、心の状態が体の機能に影響を与えやすい特徴があるパーキンソン病の診療においては患者によい影響をもたらすと考えられ、大きな意味を持つのだと言います。
金沢市のPDハウスと合同での Holomedicine 実証実験
その後、研究グループのメンバーは日本マイクロソフトの技術者とディスカッションを重ねながらプログラムを構築し、Holomedicine の動作に目処がついたのは 2019 年頃。メンバーは、まず順天堂医院内の無線 LAN 環境で実証実験を実施しました。
「100 名のパーキンソン病患者に対して、Holomedicine を用いて評価した運動症状のスコア(UPDRS partIII)を従来の対面で評価した運動症状のスコアと比較したところ、高い相関性が認められました。オンライン診療でも普段行っている診療と同じような結果を得ることができたのです」(関本氏)。
こうして後ろ盾となる実績を得た研究グループは、Holomedicine をはじめとする ICT の力を使って介護施設のなかで質の高い医療を受けられる環境づくりを目指し、PDハウスを全国で展開・運営するサンウェルズと「ICT 制御に基づく在宅医療開発講座」と名付けた共同研究講座を開始し、さまざまな共同研究を開始しました。
「当社が創業した石川県などでは、パーキンソン病の専門的な医療を定期的に受診するのはとても難しいのが現状です」と語るのは株式会社サンウェルズ 常務取締役、人事企画本部長兼サービス企画部長の長山氏。
「当社が全国で展開している施設では、神経内科の専門医に訪問診療をしてもらえる体制を整えているのですが、まだまだその質を上げる必要があります。かかりつけの先生以外の複数の先生に診てもらえる機会をつくれるという観点からも、Holomedicine には非常に期待しています」(長山氏)。

こうした現場からの期待と協力を受けながら、研究グループは Holomedicine によるオンライン診療の実現に向けて研究を推進。何度かの細かい実証実験を経て、2023 年 2 月には東京の順天堂大学と石川県金沢市にあるサンウェルズのパーキンソン病専門施設「PD ハウス小坂」との間で、同施設の利用者や近隣に住む患者を対象とした「3 次元オンライン医療相談会」が実施されました。
診療ではなく相談会という形にしたのは、まだ 3 次元映像のクオリティや通信環境の安定性が不十分と判断したからです。しかし、それでも大きな収穫があったと言います。
「なにより嬉しかったのは、患者さまの反応でした」と長山氏。HoloLens 2 越しに、まるで診察室で医師と患者が対面しているかのようなコミュニケーションが展開され、参加した患者からは「いつもの対面診療と一緒だよ」「本当に近くにいる。あっと思う瞬間に先生が消えていなくなる。こんな感覚は初めて」「田舎や島や山の上に住む人には絶対必要」といった感動の声が挙がったそうです。

Holomedicine の導入を担当した株式会社サンウェルズ サービス企画部担当部長の山﨑 結氏も、「パーキンソン病は心の影響が体に出やすい病気です。画面越しではなく、先生を近くに感じながら直接会話できる安心感は、患者さまにとって大きなメリットになると感じました」とその可能性に大きな期待を抱いたといいます。
この結果は、医療側にも大きな手応えをもたらしました。大山氏は「患者さんにも私たちの姿が立体的に見えますから、思わず私の手を握ろうとしてくるなど、2 次元では見られないリアクションがありました。構想段階から期待していた効果が見られたことは、大きな収穫だったと思います」と目を細めます。
関本氏も、「3 次元映像で得られる“同じ空間を共有している”という感覚は、信頼関係の構築に効果があるようです。これは診療において大変重要なことだと、医師として実感できました」と、Holomedicine によるコミュニケーションの有効性を評価します。
実用化に向けて課題を洗い出し、新たな機能の開発を進める
こうしてオンライン医療相談会は成功を納めたものの、Holomedicine を臨床で実用化するには、大量のデータをスムーズにやり取りできる安全かつ安定したネットワーク環境の整備や HoloLens 2 などのハードウェア、そしてアプリケーションの洗練など、まだまだ改善が必要だということもわかりました。
また、Holomedicine には「3 次元で再現できても直接触れることができない」というオンラインの宿命とも言える課題があります。その問題をカバーするために研究グループでは、ウェアラブル デバイスや Azure Kinect DKによって収集された患者の情報をAI を用いて解析し、その結果をリアルタイムで HoloLens 2 の画面に表示する機能の開発を進めています。

「これが実現できれば、オンライン診療の精度向上に加えて、専門医以外の医師による診療の質の向上にもつながるはずです」(関本氏)。
Holomedicine の実用化に向けて施設側もさらなる努力が必要、と山﨑氏。「パーキンソン病の特性上、診療においては先生と患者さまの 1 対 1 ではなく、私たちケア スタッフが関わる必要があります。今後は人的リソースの確保も含めて、もっとスムーズに機器の準備や HoloLens 2 の操作ができるような環境を整えることが大切だと感じています」(山﨑氏)。
「私たちもサンウェルズの皆さんのご協力に期待しています。全国の PDハウスに Holomedicine を設置することで、入所されている方はもちろん、近隣の患者さまも利用していただけるようになる。日本各地で専門医がいない地域の患者さまが簡単に専門医の診療を受けられる環境が実現できれば、パーキンソン病治療における大きなインパクトになると思っています」(大山氏)。
専門医とケアスタッフが一丸となって 3 次元オンライン診療の実現を目指す
今後の展望について大山氏は「まずは Holomedicine による遠隔地を結んだオンライン診療を実現すること。将来的には、診療から得られたデータを活用することで、対面を上回るクオリティの 3 次元オンライン診療を実現したい」と語ります。
その展望の根幹を担う AI 解析については「現在、部分的には症状を評価できるようになっています。全体の評価ができるように、さらに研究を進めていきたい」と関本氏。
ふたりの言葉を受けてサンウェルズの長山氏も「在宅や介護施設にいながら質の高い医療を受けられる環境をつくることで、パーキンソン病の進行を遅らせる、あるいは患者さまが寿命を全うできる病気にできるよう貢献していきたい」と決意を語ってくれました。
パーキンソン病の専門医とケア スタッフが一丸となって課題に向き合い、“3 次元で簡単に専門医に会いに行ける環境”の実現に向けて情熱を燃やす Holomedicine 開発プロジェクト。私たち日本マイクロソフトも、テクノロジの側面からより一層の支援をお届けしたいという思いを新たにしたインタビューとなりました。
“Holomedicine のプロトタイプには、まさに私たちがやりたいと思っていたことが表現されていて、感動したことを覚えています”
大山 彦光 氏, 神経学 准教授, 順天堂大学大学院医学研究科
関連の事例を詳しく見る
Microsoft でイノベーションを促進


実績あるソリューションで成果を追求




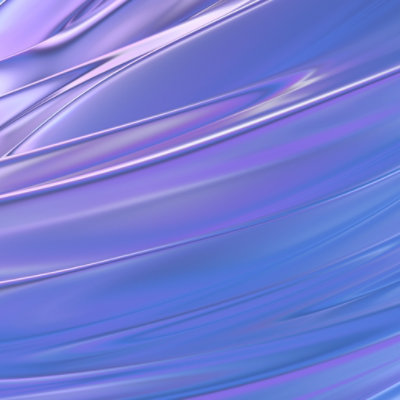

Microsoft をフォロー