「生活を支えるモビリティ企業」から「生活に密着したインフラ企業」への進化を目指しているスズキ株式会社。同社では新たな取り組みを効率的に進めるためのツールとして、生成 AI の積極的な活用が推進されています。ここで採用されているのが Azure OpenAI Service。世界的に注目される OpenAI社の ChatGPT と同様の機能を、データの安全性を確保したうえで利用できる点が高く評価されました。そのプレビュー版が登場した 2023 年 3 月には、いち早く全社展開をスタート。Azure OpenAI Service をベースに独自の汎用 Web アプリケーションを 5 種類作成し、活用の幅を広げています。その一方で、業務特化型の活用アイデアも次々と具現化。100 年に一度の変革期を限られた人員で乗り越えるためのツールとして、重要な役割を果たすことが期待されています。


早い時期から AI 活用を開始、言語系ニーズへの対応が悩みの種に
1909 年に「鈴木式織機製作所」として創業し、戦後には日本のモータリゼーションを牽引し続けてきたスズキ株式会社 (以下、スズキ)。現在では四輪車、二輪車、マリン製品を中心に、多くの国々の人々に愛される幅広い製品を開発、製造、販売しています。2023 年 1 月には 2030 年度に向けた成長戦略を発表。お客様の立場から見た「価値ある製品」作りをモットーに、机上の空論を排した「現場・現物・現実」の三現主義で行動することで、カーボン ニュートラル社会の実現を目指しています。
このような取り組みを進めるうえで、強力なツールになりつつあるのが生成 AI です。
「AI 自体への取り組みは、既に 2018 年ころから始まっていました」と語るのは、スズキ 常務役員でIT本部長を務める鵜飼 芳広 氏。2019 年にはデータ分析の重要性を強く意識し、大阪大学が開講したデータ分析講座を 10 人程度の社員に受講させる、といったことも行っていたと振り返ります。「当初は技術部門から AI 活用が始まりましたが、その後さまざまな部署で AI を使う社員が増えていきました」。
このような取り組みをさらに後押しするため、2022 年 1 月には「データ分析推進グループ」を設置。これが AI 活用の「コア チーム」になることで、全社での AI 活用が推進されるようになったのです。
「ここで大きな悩みの種になったのが、言語系のニーズが高いにもかかわらず、具体的にどうすべきかわからなかったことです」と言うのは、スズキ デジタル化推進部でデータ分析推進グループ長を務める畑 大輔 氏。既にトライはしていたものの、利用部門の要望レベルに対応できるものがなかなかできなかったのだ、と説明します。
「利用部門からの要望としては、テキスト形式で蓄積されたノウハウを活用したい、複数の担当者がバラバラに記述した文章ファイルを分類し整理したい、アンケート調査の結果をまとめたい、といったものが上がっていました」と語るのは、スズキ デジタル化推進部で部長を務める野中 彰 氏。その中でもアンケート調査は自由回答が多く、顧客アンケートだけでも月間 1 万件前後の回答を得ていたため、人力での分析は限界があったのだと言います。
このような悩みを抱えながら、幅広い調査を行ったうえで着目したのが、ChatGPT でした。
「他にもさまざまなテキスト系アプリケーションをチェックしてきましたが、2022 年 12 月に ChatGPT の盛り上がりを見て、大きな可能性を感じました。そこでまずは使ってみようと考えました」 (畑 氏)。
実際に ChatGPT を使ってみると、かなり便利なものであることが判明。しかし企業として使うには、いくつかの問題もあることがわかったと畑 氏は指摘します。その 1 つが、入力した情報 (プロンプト) が社外で共有されてしまうため、企業として使うにはセキュリティ面での不安があったことです。
その後、2023 年 3 月にマイクロソフトが ChatGPT と同様の生成 AI 機能を Azure 上で活用できる「Azure OpenAI Service」のプレビュー版をリリース。スズキはこのタイミングで Azure OpenAI Service の利用を開始したのです。

データ安全性を評価し Azure OpenAI Service を採用、汎用的に使える 5 つのアプリで全社展開を推進
「Azure 上で使用できるのであれば、データ保護に関する不安はありません」と畑 氏。この問題を解決できるのであれば、あと 2 つの課題をクリアすれば、全社展開が可能になると判断したと言います。
1 つは全社利用するうえでの「ガイドライン」の策定とその周知。そこで重視されたのが、著作権を侵害しないことと、生成 AI が出す回答を鵜呑みにしないことでした。「生成 AI が嘘をつくこと (ハルシネーション) があるのはわかっていました。そのため生成 AI の回答だけで判断するのではなく、”三現主義1 “ の精神で自分の目で確かめることを前提に、自由に使ってもらうことにしました」。
1 机上の空論を排した「現場・現物・現実」を重視する行動様式
もう 1 つは、高度な IT 知識がない一般社員でも自由に使えるように、ユーザー インターフェイス (UI) を整備しておくことです。
「データ分析推進グループがオンプレミスでサーバーを持っていたので、Web アプリケーションを作成してこの上で動かすことにしました」と言うのは、スズキ デジタル化推進部 データ分析推進グループで係長を務める大芦 信太郎 氏。フロントエンドの部分は HTML5 と JavaScript、Azure OpenAI Service の API へのアクセスは Python で作成していると語ります。「2023 年 3 月 9 日にマイクロソフトが API を公開してから、約 2 週間で最初のアプリを完成させることができました」。
これと並行して、経営会議で「安全な生成 AI 環境を Azure OpenAI Service で構築/リリース」することを報告。三現主義を重視したガイドラインの策定と、データの安全性を確保した環境が認められ、3 月 21 日には全社展開が開始されます。
この全社展開と同日に提供されたのが、大芦 氏が最初に作成したアプリ「NAGI」です。そして、その 1 週間後には ChatGPT と同じように対話型で直接プロンプトを入力して回答を得るアプリ「NAMI」の提供も始めました。「とにかく重要視したのは圧倒的な使いやすさです。例えば NAGI は、一問一答型のチャット アプリで、『翻訳して』『要約して』といった代表的なプロンプトをボタン化し、簡単に使えるようにしています」 (大芦 氏)。
NAGI 、NAMI の他にも、ChatGPT に仮人格を与え、その人格同士が議論を行うアプリなど、さまざまな Web アプリが提供されています。
NAGI | 一問一答型チャットアプリ。『翻訳して』『要約して』などプロンプトをボタン化 (2023 年 3 月 21 日に提供 開始) |
NAMI | ChatGPT と同じように対話型で直接プロンプトを入力して回答を得るアプリ (2023 年 3 月 28 日に提供開 始) |
「いずれも便利なアプリですが、なかでも ChatGPT の仮人格同士が議論を行うアプリは面白いです」と言うのは鵜飼 氏です。スタートアップの経営者、弁護士、コンサルタント、主婦、小学生、Youtuber など職業・国籍・性別の違う合計 26 人分の人格を用意しており、それらの人達と仮想会議をすることで、それまで気付けなかったことに気付かされることが少なくないのだと言います。「その人達との 1 対 1 の会話も可能で、悩んだときの相談相手や外国語学習の先生になってもらうことも可能です。生成 AI を活用していく中で、新たなアイデアが生まれることにも期待しています」。
また、役員への DX 研修に生成 AI を使う、という取り組みも行われています。「対話型で生成 AI に指示を出してもらい、それに基づいて生成 AI がプログラムコードを生成する、という体験をしてもらいました。指示が適切でなければ、正しく動くコードになりません。これは、部下に対する指示も全く同じだ、という気付きにもつながったようです」 (鵜飼 氏)。
なお、NAGI と NAMI の名称は、日本書紀に登場する神様が基になっていて、NAGI はイザナギ、NAMI はイザナミから取られていると説明します。日本書紀ではあらゆる神様がイザナギ、イザナミから生れていったように、このアプリを使うことでさまざまなアイデアやイノベーションが生まれていって欲しいとの思いが込められていると大芦 氏。


年度末でも可能だった全社展開、活用アイデアの具現化もマイクロソフトが支援
ここまで紹介したものは汎用的に使えるアプリですが、業務に特化した使い方も既に始まっています。その一例として挙げられたのが、インドにおける人材採用の効率化です。
「インドでの人材募集は面接に入る前に 2 日程度で書類選考を行う必要があるのですが、数名の枠に 100 名を超える応募が来ることもあります。ここに生成 AI が使えないかと採用担当者から相談を受け、採用したい人物像との合致度を数値化し、全員分の数値をマッピングしました。実際にこれで書類選考し、3 ~ 5 名に絞り込んで面接を行った結果、まさに当社が望むような人材を引き当てることができたので、人材採用の担当者から『すごい!』と感嘆の声を聞くことができました」 (野中 氏)。
また、生成 AI を用いて、社内ドキュメントを質問形式で検索できる取り組みや、会議音声からテキストを起こし、これを要約して議事録を作成するといった取り組みも各所で始まっています。各々の社員がアイデアを出し合い、生成 AI をうまく使いこなしていくことで、単純作業やルーチン ワークにかけている工数を 80% 削減できると期待されています。
「このように生成 AI 活用に関しては、社内からさまざまなアイデアが出ていますが、それらを具現化するためのサポートをマイクロソフトから受けられることも、Azure OpenAI Service 採用の大きなメリットです」と畑 氏。特に、社内ドキュメントの検索をどう行うべきかに関しては、重要なヒントを複数もらったと言います。
これに加えて、導入時に追加コストが掛からなかったことも、Azure OpenAI Service の魅力の 1 つだと指摘するのは野中 氏です。
「全社展開を決めたのは 2023 年 3 月ですが、通常であればこの時期は年度予算を使い切っており、新たな取り組みは次年度になることが一般的です。しかし Azure OpenAI Service は、既に契約済みだった Azure ライセンスの中で利用できるため、新規予算を計上する必要がありませんでした。そのためすぐに、全社展開へと踏み出せたのです」。
スズキでは今後も、生成 AI がどんどん日常的な業務の中に入り込み、人と AI が連携することで、飛躍的な生産性向上が可能になると期待されています。近い将来には社内業務だけではなく、車に組み込まれたコネクテッド サービスを通じて、顧客への情報提供を生成 AI で行うことも視野に入っています。その一例として挙げられたのが、音声で観光案内を行うカーナビ アプリの提供です。Azure OpenAI Service は取り扱える言語の幅が極めて広く、ヒンディー語を話すことも可能であるため、スズキが注力する国の 1 つであるインドでの展開も容易だと評価されています。
「今の自動車業界は 100 年に一度の変革期です」と鵜飼 氏。そのため新しいことに数多く取り組む必要がありますが、そのための人が足りないという状況だと言います。「限られた人員で新しいことに取り組むには、業務そのものの効率化に加えて、人がやるべきことは何かを明確にし、やる必要のない仕事を減らしていく必要があります。AI はそのために有効なツールです。いまはまだスタートラインに立った段階ですが、これからも新しいテクノロジーを使いこなしながら、人のポテンシャルを高めていきたいと考えています」。

“100 年に一度の変革期を限られた人員で乗り越えるには、業務そのものの効率化に加え、人がやる必要のない仕事を減らしていく必要があります。AI はそのために有効なツールです。これからも新しいテクノロジーを使いこなしながら、人のポテンシャルを高めていきたいと考えています”
鵜飼 芳広 氏, 常務役員 IT本部長, スズキ株式会社
関連の事例を詳しく見る
Microsoft でイノベーションを促進





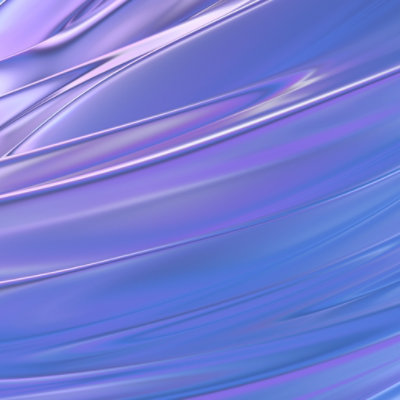

Microsoft をフォロー