

既に 2018 年から RPA を活用、その後のコロナ禍でデジタル化が一気に加速
1882 年に創立し、多種多様な業界で活躍する人材をこれまでに 60 万人以上も輩出してきた早稲田大学。創立者の大隈重信が宣言した「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」という早稲田大学教旨は、現在でも多くの学生、校友 (卒業生)、教職員に引き継がれています。2012 年 11 月には、創立 150 周年を見据えた「WASEDA VISION 150」を発表。さらに 2020 年 1 月には、「WASEDA VISION 150 AND BEYOND」を発表し、2040 年には日本で、2050 年までにアジアで、最も学びたい大学だと、世界中の人々から思われる大学になることを目指しています。このビジョンを実現するための重点施策の 1 つとして進められているのが、IT を活用した学内業務の改革です。
「WASEDA VISION 150 の発表に先立つ 2011 年には、『業務構造改革プロジェクト』がスタートしていました」と語るのは、 早稲田大学 情報企画部の阿部 慶太朗 氏。その一環として、学内の複数キャンパスや複数部門の経理処理共通業務を集約した「アカウンティングセンター」が設置されたと振り返ります。「早稲田大学には約 130 の部門があるのですが、これらの部門それぞれで行っていた経理処理業務を段階的にアカウンティングセンターへと集約し、効率化を進めてきたのです」。
2014 年にはシステム開発の根本思想を見直したうえで、2018 年の本番稼働を目指した「次期法人系システムの導入プロジェクト」もスタートします。しかし、プロジェクトの途中で業務処理内容の拡大が検討されたことで、新システムの業務効率化効果を上回る処理量になることが判明。この問題を解決するため、RPA による生産性向上に向けた取り組みが開始されることになります。まず RPA に関する情報収集を 2017 年 4 月に開始し、複数の RPA 製品の中から 1 つを選択、10 月から検証に着手します。ここでまず行われたのが、年間 20 万件以上ある支払伝票のシステム登録自動化でした。
「もともとはスプレッド シートで作成した伝票を紙に出力し、そのうえで形式チェックや論理チェック、システムへのデータ登録を手作業で行っていたのですが、この部分を RPA で自動化することで、年間 3 万時間以上の工数削減が可能になりました」 (阿部 氏)。
この成果を受け 2018 年 4 月には、この RPA 製品を全学で活用することに決定。2019 年度までには 50 以上の業務で、ロボットの開発および活用が行われています。
しかし新型コロナ ウイルス感染症が拡大し、オンライン授業への切り替えや各キャンパスへの立入禁止などが始まったことで、早稲田大学におけるデジタル活用は大きな転機を迎えることになります。これに伴い、RPA 活用のスタンスも大きく変化していくのです。
「コロナ禍への対応でまず行われたのが、教員や学生をサポートするための情報提供サイトとチャット ボットの立ち上げでした」と語るのは、早稲田大学をはじめとする大学固有の業務アウトソーシングや教育、研究支援などを行う株式会社 早稲田大学アカデミックソリューション (以下、早稲田大学アカデミックソリューション) で、代表取締役 社長執行役員を務める神馬 豊彦 氏です。また 2020 年 10 月には証憑電子保管システムや勘定科目類推 AI を導入し、2021 年 4 月には生協とのデータ連携と AI/RPA 連携を実現、2021 年 6 月には電子契約システムも導入していると説明します。
「2021 年 9 月には職員用 PC を刷新し、Microsoft 365 と Microsoft Intune を展開。これに伴い、Microsoft Teams や Microsoft SharePoint などの活用も急速に広がっていきました。なお、電子契約システムの本格導入の際には、署名済契約書の自動保管を Microsoft Power Automate で実現しています」。

大きく変化した業務自動化への考え方、その実現のために Power Automate を採用
「このようにデジタル化が短期間で一気に進んだことで、業務自動化に対する考え方も変わっていきました」と神馬 氏。2019 年 10 月に米 Gartner 社が、AI やパッケージ サービス、RPA などを組み合わせて一連の業務を実行する「ハイパー オートメーション」をいう概念を提唱していましたが、早稲田大学でも単に RPA を使うだけではなく、ハイパー オートメーションを目指すべきという方向性に変化していったのだと言います。
「2022 年度までには 120 程の業務で RPA が利用されていましたが、これらはバックエンド業務の自動化にとどまっていました。学生や保護者、校友、教職員といった大学のステークホルダーの皆様が、いつでもどこでも、より早く、より簡単に、やりたいことを実現するには、もっと柔軟な体制を構築する必要があると考えました」 (神馬 氏)。
そこで 2022 年 4 月に「職員業務トランスフォーメーション推進プロジェクト」をスタート。共通業務に関しては「ステークホルダーへのサービス向上と事務の効率化」、個別業務に関しては「専任職員が自分自身で自動化を推進」という方針を掲げた取り組みが始まります。そしてそのメジャー ツールとしては、Power Automate を採用することに決定するのです。
採用理由は大きく 2 つあると説明するのは阿部 氏です。1 つは、Power Automate は Microsoft 365 に含まれるため、まずはその範囲で可能なことから始めることで、ライセンス費用を低く抑えられること。もう 1 つは、IT の専門家ではなくても簡単に利用できることです。「他の RPA 製品でも利用部門開発を推進していましたが、従前の RPA を適用した 120 程の業務のうち、そのほとんどは開発チームが開発したものであり、利用部門開発は 20 業務にとどまっていました。Power Automate なら自分たちで作って自分たちで使うことで、スピード感のあるサービス提供が可能になると考えました」。
もちろん利用部門開発を推進するための支援も、積極的に行われています。「職員自身による業務電子化/自動化トレーニング」のコンテンツを制作し、全職員に向けて公開。日常的な助け合いや教え合いを可能にするため、Microsoft Teams 上に設置したチームによるオンライン コミュニティも提供しています。また、トレーニングからプロジェクト立ち上げ、業務分析、新業務フロー検討、機能開発、運用保守、環境整備、ショーケースという、8 つのフェーズで構成される「現場部門 DX 推進サイクル」も明確化。さらに、Power Automate や Teams、SharePoint などを含む利用部門向け環境も整備されています。
「新たな業務自動化は Power Automate で実現しています」と言うのは、早稲田大学アカデミックソリューション IT推進部 IT-Xチームの櫛渕 倫太郎 氏。2022 年度だけで 220 の業務で利用されており、2024 年 2 月までに 400 を超える業務トランスフォーメーションが実現されたと言います。


急速に進みつつある業務変革、今後もマイクロソフト製品をベースに「LCAP」の実現へ
その一例として「銀行口座振込依頼書送付/口座登録業務」の自動化を紹介するのは、早稲田大学 財務部 経理課の清水 研三 氏です。
「大学には、例えば学外の方に謝礼などを支払うために、銀行口座振込依頼書をいただき、その口座情報を財務システムに登録する業務がありますが、以前は紙の用紙に記入し捺印したものを郵送していただき、それをスプレッド シートに転記してから RPA で登録していました。現在では学外の方に電子署名システムで入力していただき、Power Automate や Microsoft Forms、SharePoint を連携させることで完全に電子化しています」。
そのフローは図 1 に示すとおりです。まず学外の方への口座情報入力の依頼と学内関係事務所への確認依頼を図の上側にある「フロー 1」で実施。ここで使用されている Power Automate は、電子署名システムの Adobe Acrobat Sign が利用されています。入力内容が確定すると、「フロー 2」によって入力内容を SharePoint 上の Excel ファイルに保管。「フロー 3」で、Power Automate が財務システムへの登録を行います。
「このうちフロー 3 は学内システムとの連携が必要になるため情報企画部に作成をお願いしましたが、他のフローはすべて私が作成しました。このしくみによって業務工数は 5 ~ 6 割削減され、学外の方への依頼からシステム登録までの時間も、最短 1 週間から 20 ~ 30 分に短縮されています。また転記ミスや紙の紛失リスクもなくなりました」 (清水 氏)。
これに加えて櫛渕 氏は、「経理処理電子申請化」の取り組みも紹介します。これは改正電子帳簿保存法の施行を受け、2023 年 4 月から順次稼働を開始しているもの。教員・予算管理部門が電子的に受領した証憑を、紙に印刷することなく電子申請し、部門内承認や経理処理部門への回付もすべて電子的に完結できるようにしているのだと言います。
「この他にも、Form Recognizer (現在の Azure AI Document Intelligence) を活用した OCRや、Azure Logic Apps と Azure Automation を連携させた QR コード読み取り/PDF ファイルの分割および統合なども行っています。さらに、Power Automate for Desktop の環境を Azure Virtual Desktop 上で動かし、仮想マシンを Power Automate のキュー数に応じて、オンデマンドで起動かつ停止するフローも実現しています」 (櫛渕 氏)。
今後はその効果をさらに引き出すため、これまで使ってきた既存の RPA 製品を Power Automate に移行することも計画しています。既に移行支援サービス「Blueprint」 (カナダ Blueprint Software System Inc.) を活用した移行検証も進められています。
「職員業務トランスフォーメーション推進プロジェクトで目指しているステークホルダーへのサービス向上と事務の効率化には米 Gartner 社が提唱する LCAPの採用が重要となります」と神馬 氏。そしてこれは、RPA による自動化やノーコード/ローコードでのアプリ開発だけではなく、複数のクラウド サービスやチャット ボット、AI なども連携して活用し、市民開発者とプロ開発者が協力してシステム全体を構築する基礎を作り上げることを意味しているのだと説明します。「マイクロソフトはこの LCAP の世界でリーダー的な存在です。これからもマイクロソフトのテクノロジーを積極的に活用しながら、業務トランスフォーメーションの領域を拡大していきたいと考えています」。

“職員業務トランスフォーメーション推進プロジェクトのメジャー ツールに Power Automate を採用した理由の 1 つは、ライセンス コストを削減できることです。また自分たちで作って自分たちで使うことで、スピード感のあるサービス提供が可能になると考えました”
阿部 慶太朗 氏, 情報企画部, 早稲田大学
関連の事例を詳しく見る
Microsoft でイノベーションを促進


実績あるソリューションで成果を追求










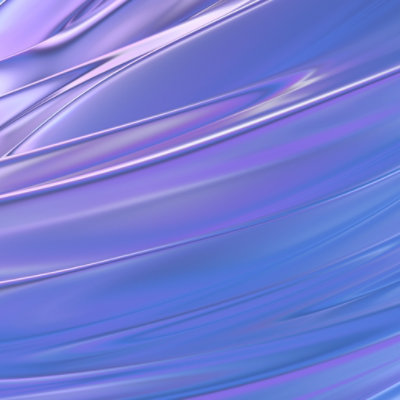

Microsoft をフォロー